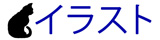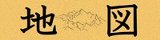■薄紅の花 04.河口の街-35.移ろう季 (2016年01月03日UP)
風が緩み、海が微睡(まどろ)んでも、商船は帰港しなかった。
三人は海龍号のことを口にしなくなり、淡々と日々を送っている。
心配を口にしてもしなくても、朝には陽が昇り、時が来ればまた沈む。気持ちは冬至祭で足踏みしたまま、時間だけが積み重なって行った。
咲く花の色が変わり、木々の緑が濃くなっても、商船海龍号は入港しない。
商品が夏物に入れ替わり、また、防虫剤や蚊除けを作る日々が始まった。
おかみさんは店に出ている間は、いつも通りに振舞っているが、奥へ引っ込むと、途端に口数が減った。
井戸端では、寒い内こそ、三兄弟の帰郷が話題に上ったが、最近はおかみさんに気を遣ってか、何も言われなくなった。単に飽きたのかもしれないが、そっとしておいてもらえることが、有難かった。
例のタカリはその後、姿を見せず、双魚は再び店番に立つようになった。
おかみさんの留守中、時折、三兄弟の近況を尋ねる客もあったが、双魚が首を横に振ると、申し訳なさそうに苦笑して、肩を落とした。
「そうだな。あんな騒々しい連中、帰って来てわからん筈ないもんな」
夏至祭が巡って来たが、商船海龍号が今、どこの港に居るのか、何の話も耳に入らない。
近くの港を往復する貨物船や遠く沖合に出る漁船は、何の知らせももたらさなかった。
「まぁ、あれだ。夏至祭は女房子供と過ごしてるからな。あっちで宜しくやってるだろう」
「そうだねぇ。風待ちの間に荷が傷んじゃうから、手前の港でみんな降ろして、そのまま折り返したのかも知れないしねぇ」
最近、すっかり老けこんだ夫婦が、お茶を飲みながら言った。
凪の海のように平坦な日々が続いている。
例年通りやって来た三ツ矢は、話を聞いて申し訳なさそうに頭を掻いた。
「俺の里は反対方向だからなぁ。街で何か聞けたら、話す。便りがないのは元気でいるからかも知れん」
如何に屈強な魔法戦士とはいえ、こんな時には、気休めを言うくらいしか出来ない。
錨院長に頼まれた件についても、良い返事はもらえなかった。
「双魚じゃ断り難いだろう。俺が行って直接、断るよ」
亭主の案内で双魚も同行し、三人で医院に行った。久し振りに訪れた医院は、何も変わっていなかった。
三ツ矢は、正直に事情を打ち明け、丁重に断った。
「すまんな。何せ、小さな村なもんで、こちらも人手が足りぬのだ」
「そちらにはそちらのご事情がおありですし、こちらこそ、ご無理を申し上げまして恐れ入ります」
錨院長は落胆したものの、腹を立てることはなかった。
三ツ矢は残りの数日、用事を片付けるついでに、商船海龍号について何か噂でもないか、雑貨屋夫婦が普段行かない所を巡って過ごした。結局、何の情報も掴めないまま、いつもの日数で里へ戻った。
双魚は久し振りにアーモンドの夢を見た。
どこかの波打ち際で、沖を見詰めている。
背後から風が吹き、花弁が波に散る。泡立つ海が、薄紅に染まる。
寄せては返す水面を漂い、薄紅の花弁が沖へ、沖へと流れて行く。
出られれば、探せるのに……
双魚自身が思ったのか、背後に立つ誰かの言葉なのか、定かでない思いが、水平線の彼方へ視線を誘う。海へ出られれば探せるのに。
目が覚めた時、探しに行きたい、との思いが双魚の中に強く残った。
……そりゃまぁ、猫島さん達はもっと、そう思ってるだろうけど、お店もあるし、探しに行くとなったら……俺……かなぁ?
東の港へ探しに行き、消息が掴めれば【跳躍】でここに戻る。向こうで暫らく過ごして、場所を心に刻めば、東のどこかにあるその港へ戻るのも、瞬く間だ。
店を離れる期間がどのくらいになるか、予測がつかず、契約がどうなるのかもわからない。雑貨屋だけでなく、医院との契約もある。
丁度、おかみさん不在の折に医院の使者が来た。納品の後、双魚は思い切って聞いてみた。
「私では判断致しかねますが、必ずしも良い知らせになるとは限りませんからね。もうしばらく、様子を見られては如何ですか?」
使者は、材料が入荷しないことから、商船海龍号が帰港しなかったことを知っていた。
即答した使者の様子に、双魚は医院でも情報収集しているのか、と思った。詳しく聞いたものかどうか、迷っている内に、使者は店を辞してしまった。
じたばたしたところで、状況が変わる訳じゃないし、待つしかないよな……
今日帰るか、明日はどうか。
おかみさんは、一日一日、夜が明ける度に港へ行き、店の準備に戻り、夕方、双魚に店を任せて市場へ行く前にも、港へ行った。
一日、一日、夜が明ける度に期待を寄せ、日が沈む度に落胆する。足元だけを見詰めて歩むるように、一日ずつ、時を待って暮した。
冷たい風に木の葉が散り、日が短くなってきた。
また、今年も冬至祭が巡って来る。
雑貨屋の商品も祭用の品が増えた。
今年も帰って来なかったら……いや、今年は帰って来る。
悪い予感を打ち消し、希望に縋りながら、冬至祭の日を指折り数えて待った。